エーーーーー。オーナーの方から了解が得られましたので・・・・・。

さあ、作業に入ります。今回、特に手を焼く部分は有りません。工数は多いですが、楽な仕事の部類です。
で、アンプを裏返し。
裏からの写真・・・・・・・・・・。
左端?

訳の判らないスプリングが顔を出して・・・・・。
此処でピンと来たら、かなりの愛読者(笑)。

底板を取ると・・・・・。
ナント真空管が2本、クランプされています。
そう、通常の僕のプリアンプ。此処には真空管は入っていません。
オーナーの悪戯(ウソウソ、叱られてしまう)。
エーー、ヘッドアンプ内蔵なのです。
此れが世界で1台のアンプの正体。2台作ったのですが(一台は店頭用)、其の店頭用はバラされて跡形も有りません。
本当に1台きりです。
で、僕がそれ以上作らなかった理由・・・・・。

判ります?ラグ。1本1本、シャシに立っているのです。この為に、シャシに切ったネジ穴。百数十本。
兎に角、イヤに成りました。よく間違えずに切ったと自分でも感心。
もう、ダレも頼まないでね(大汗)。
当時、ブロックケミコンの音の悪さに気付き、チューブラコンへの変更時期だったのです。
もし、アンプを弄っている方。2~3本同梱してあるブロックケミコンを、チューブラコンへ改造して見て下さい。
音は間違いなく良く成ります。ブロックケミコンを百叩きの刑にしてやりたい。
でも・・・・・・・・・・。
ブロックケミコン、配線のし易さは天下一品。メーカーは使う筈だよねー。って無茶苦茶気付く筈。
で、苦心末のラグ配置だったのです。

全体像。
もう作りたくない・・・・・・。
さあ、作業に入ります。今回、特に手を焼く部分は有りません。工数は多いですが、楽な仕事の部類です。
で、アンプを裏返し。
裏からの写真・・・・・・・・・・。
左端?
訳の判らないスプリングが顔を出して・・・・・。
此処でピンと来たら、かなりの愛読者(笑)。
底板を取ると・・・・・。
ナント真空管が2本、クランプされています。
そう、通常の僕のプリアンプ。此処には真空管は入っていません。
オーナーの悪戯(ウソウソ、叱られてしまう)。
エーー、ヘッドアンプ内蔵なのです。
此れが世界で1台のアンプの正体。2台作ったのですが(一台は店頭用)、其の店頭用はバラされて跡形も有りません。
本当に1台きりです。
で、僕がそれ以上作らなかった理由・・・・・。
判ります?ラグ。1本1本、シャシに立っているのです。この為に、シャシに切ったネジ穴。百数十本。
兎に角、イヤに成りました。よく間違えずに切ったと自分でも感心。
もう、ダレも頼まないでね(大汗)。
当時、ブロックケミコンの音の悪さに気付き、チューブラコンへの変更時期だったのです。
もし、アンプを弄っている方。2~3本同梱してあるブロックケミコンを、チューブラコンへ改造して見て下さい。
音は間違いなく良く成ります。ブロックケミコンを百叩きの刑にしてやりたい。
でも・・・・・・・・・・。
ブロックケミコン、配線のし易さは天下一品。メーカーは使う筈だよねー。って無茶苦茶気付く筈。
で、苦心末のラグ配置だったのです。
全体像。
もう作りたくない・・・・・・。
抵抗の交換だけの予定だったアンプ。
僕の余計な一言。
ピ『トランスのスットク、有りますよ。』
聞かされる方には、手招きされている様に聞こえたんだろーなー・・(汗)。
抵抗交換と同時に、出力トランスを付ける事に成りました。
正直、最終的には付けるんだし、其の場合、貴重な抵抗器をまたもや交換。抵抗器を無駄にしないで済みますし・・・。
昨日は、写真のアルミのプレートを作っていたのです。
これから、作業開始。
でも、後ろで鳴っているレコード。ドンドン調子が上がっている。
ツ・ラ・イ・・・・・・・。
考えたら此処10日間ほど、自分の装置のグレードアップだけ。
そりゃ、自分の装置の音が良く成るのは嬉しいけど・・・・・・。
早い話、見入りゼロ。
オイオイ、やばいよ。
でーーーーーー。

以前に頼まれていた仕事です。
写真の抵抗器。右は御馴染みアーレンブラットレイ。有名な米国製のアンプは、殆ど此れが使われています。
国産のアンプでも、此れを使っているのをうたい文句にしている物も。
僕も、店を開けて20年近く愛用。
確かに国産金皮よりは良かった。
でも、問題点も沢山。
まず値がいい加減。金帯を付けちゃいけないですね。
ノイズレベルも大きい。でも音色が金皮よりは好ましいので、使っていました。
何時までもA&Bに負ぶさっている訳にも行かず、散々探して見つけたのが左の抵抗。
残念ながらこれも2~3年前に生産完了。
完了間際に、出来るだけかき集めた。
今回の仕事。
このアンプ10年ほど前の作品。
抵抗は全てA$B。
此れを全て左の抵抗に交換です。
何個交換なのかなー。
頑張ろう。
そりゃ、自分の装置の音が良く成るのは嬉しいけど・・・・・・。
早い話、見入りゼロ。
オイオイ、やばいよ。
でーーーーーー。
以前に頼まれていた仕事です。
写真の抵抗器。右は御馴染みアーレンブラットレイ。有名な米国製のアンプは、殆ど此れが使われています。
国産のアンプでも、此れを使っているのをうたい文句にしている物も。
僕も、店を開けて20年近く愛用。
確かに国産金皮よりは良かった。
でも、問題点も沢山。
まず値がいい加減。金帯を付けちゃいけないですね。
ノイズレベルも大きい。でも音色が金皮よりは好ましいので、使っていました。
何時までもA&Bに負ぶさっている訳にも行かず、散々探して見つけたのが左の抵抗。
残念ながらこれも2~3年前に生産完了。
完了間際に、出来るだけかき集めた。
今回の仕事。
このアンプ10年ほど前の作品。
抵抗は全てA$B。
此れを全て左の抵抗に交換です。
何個交換なのかなー。
頑張ろう。
昨日はヒーター電圧の測定で時間切れ。
今日はB電源を繋いで、最終チェックです。
電源SWをON。
テスター棒を素早く移動し、各真空管に正常な電流が流れているかを測ります。
1本の真空管に手間取っていると、異常電流の流れている真空管を駄目にしかねません。
さっさと測るのが重要。
で、各真空管。見事計算どおり。なんせ、電源が違うのですから、中々計算通りに行かないのが普通。
要は計算値に対して、チョットずらした抵抗値で組みます。このサジ加減具合は経験で覚えるしか有りません。
電流値が決ればもう安心。これからはユックリと測定。
フォノ入力に1kHzの正弦波を入力します。
見辛いですが、オシロの波形はイコライザー段の出力波形。
上下(左右ch)の波高値が揃っています。重ねるとピタリ。
ノンNFですから見事。
増幅率は1kHzで40dB。
このぐらいのゲインは欲しいですね。
出来上がったアンプは、試聴の前にこの様な健康診断が必要です。
耳での好みの前に、まず健康体。
特に、人様に渡すアンプですから。
さあ、これから仕上げ。配線のバインドです。
今日中には完成です。
昨日の頑張りで、パネルが遂に付きました。
パネル周りの配線、特にロータリーSW周りは結構大変なのです。
信号の切り替えと、発光ダイオードの切り替えをします。
何度やっても、間違わないように気を使う配線です。
ウッカリ、パネルに傷を付けたらオーマイゴット。
ズボンのベルトも外しての作業に成ります。バックルの金属が怖いんですね。
残るはAC電源周りだけに成りました。
で、実は此処も大変なのです。
VRの直ぐ傍に電源SW。要は信号ラインとACが近くを走る。
全然気にしないアンプも見かけますが、僕には重要。
信号ラインではなく、ACラインにシールドケーブルを使い対処します。
此処数週間。掛かりっ切りのプリアンプ。
なんせ、シャシの削り出しから始めるのですから、チョチョイノチョイとは行かないのです。
更に今回は、A電源を内蔵しないといけなく成りましたから尚更です。
今朝の状態。
基本配線(B回路、アース回路、信号ライン)が終え、CR類の取り付けに成りました。
アース母線を使いませんので、アース配線の多さが目立ちます。こげ茶色の配線が其れです。
B回路の配線も共通インピーダンスを持たせない配線ですので、配線の本数はドンドン増えます。
プリント基板では出来ない配線ですね。
更にブロックケミコンも排除。
ブロックケミコンは兎に角配線処理がやり易い。ブロックを使うのを止めた当時、配線処理に手こずりました。
カソードのパスコンだけはケミコンを使いますが、それ以外は全てフィルムコン。
すごく贅沢なアンプなのです。
でも、其の贅沢さ。音に反映しなければ只の自己満足。
確実に反映する自信(過去の沢山の実験)が有るからこその採用です。
これから、大物のフィルムコンを取り付け、パネルの配線に入ります。
今掛かっている、プリアンプ。
外注に頼んでいましたフロントパネルが出来上がりました。
パネルの製作には結構時間が掛かります。
まず最初に、僕がアルミ板から切削。
切削の終わったパネルをアルマイト屋さんに出す。
アルマイトの掛かったパネルを彫刻屋さんへ。
僕が切削に掛かってから、出来上がるまで2週間。
量産品ではこんなに手の掛かる事はやっていられませんね。
今回のアンプ。パネルの高さが従来の物より5cm程高い。
今迄でしたら、下のつまみの周りの彫刻で其れ成りにバランスの取れたデザインでした。
今回は上が長いのです。上半分が間延びした感じに成ってしまいます。
で、ロゴをその辺を落ち着かせる位置に彫りました。
着色はお客様の希望のグレー。
パネルの色に合う様に、彫刻屋さんが調合してくれたグレーです。
オーダーメイドのアンプ、チョット贅沢ですが、楽しみも大きいのです。
さあ、配線開始。
最近、オーディオの方の更新が無くてバイクばっかり。遊んでいるな。
って、思っている方。ブッブー。
シッカリ仕事もしています。
先週は一日も休んでいませんでしたし。
で、今の仕事。軽い気持ちで受けちゃったけど、予想外に手こずっています。
全て新しく作るのでしたら、今迄何台も作っていますので、迷いません。
今回は、前から有る電源を利用してと言う課題です。
先にアップした電源。良く出来ていますが、僕の思い違い。
B電源だけでA電源が入っていない。
そうなんです。今迄使っていただいたアンプ。本来の形は電源内蔵です。
勿論シャシに内蔵ですから、そんなに余裕タップリとは行きませんし、B回路にチョークも入っていません。
それで、強化別電源がオプションに有ったのです。
と言う訳ですので、A電源は内蔵電源を其の侭利用。
強化電源はB電源のみ。
さて困った。A電源を別電源かアンプ本体に付けなければいけなくなったのです。
散々考慮。結果はアンプ本体にA電源を付けよう。

穴あけ加工の終わったアンプ天板。
左奥の大きめの穴がA電源用のトランスを付ける穴。
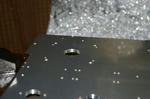
其の部分のアップ。
単にトランスを付けるだけではなく、A電源は直流ですから、整流回路も入れなければ。
そんな色々と入れられる様な大きなシャシを使っていたら、設計者の腕が疑われます。
余裕の無いシャシの中に、他への影響を出さない位置への配置。
かなり考えました。
更に、トランスの高さが結構有ります。パネルの奥にトランスが見えるのはかっこ悪い。
結果、パネルの高さも増やしました。
一品物ってこんなものです。十分な時間を使ってジックリ考えないと、作っている間にオーマイゴットが・・・・・・。
パネルとツマミのアルマイト加工も上がってきました(パネルはとっくに作っていたのですね)。
連休明けには彫刻屋さんへ出します。
其れ迄にリアパネルも作らなければ・・。
って、思っている方。ブッブー。
シッカリ仕事もしています。
先週は一日も休んでいませんでしたし。
で、今の仕事。軽い気持ちで受けちゃったけど、予想外に手こずっています。
全て新しく作るのでしたら、今迄何台も作っていますので、迷いません。
今回は、前から有る電源を利用してと言う課題です。
先にアップした電源。良く出来ていますが、僕の思い違い。
B電源だけでA電源が入っていない。
そうなんです。今迄使っていただいたアンプ。本来の形は電源内蔵です。
勿論シャシに内蔵ですから、そんなに余裕タップリとは行きませんし、B回路にチョークも入っていません。
それで、強化別電源がオプションに有ったのです。
と言う訳ですので、A電源は内蔵電源を其の侭利用。
強化電源はB電源のみ。
さて困った。A電源を別電源かアンプ本体に付けなければいけなくなったのです。
散々考慮。結果はアンプ本体にA電源を付けよう。
穴あけ加工の終わったアンプ天板。
左奥の大きめの穴がA電源用のトランスを付ける穴。
其の部分のアップ。
単にトランスを付けるだけではなく、A電源は直流ですから、整流回路も入れなければ。
そんな色々と入れられる様な大きなシャシを使っていたら、設計者の腕が疑われます。
余裕の無いシャシの中に、他への影響を出さない位置への配置。
かなり考えました。
更に、トランスの高さが結構有ります。パネルの奥にトランスが見えるのはかっこ悪い。
結果、パネルの高さも増やしました。
一品物ってこんなものです。十分な時間を使ってジックリ考えないと、作っている間にオーマイゴットが・・・・・・。
パネルとツマミのアルマイト加工も上がってきました(パネルはとっくに作っていたのですね)。
連休明けには彫刻屋さんへ出します。
其れ迄にリアパネルも作らなければ・・。
