小物パーツを付け終えてふと気が付いた。
トランスケースの穴開けは大丈夫だろうか?
今回、シャシの外に10個のトランスが付きます。
裸のトランスですからケースは必須(高圧が掛かっている端子がむき出し)。
なにしろ2年以上前に引いた図面です。細かな穴位置が・・・・・・・。
仮組みをして確認です。

エーーー、バッチリ。と言いながらOPTケースの側板を作っていないのに気付いたりして・・(大汗)。
外寸は出来ているので穴開けネジ切りだけです。
写真の説明。
細長い2個のケース。イコライザー段のトランスが片側3個入ります。
手前の中途半端な壁がOPTケースの一部。
穴が4個開いていますが、此れは出力端子の穴です。
トランスから出ますから、シャシに穴を開けると配線が長くなります。
ケースに付けてしまえば簡単です(実はこれも忘れていて・・・・汗)。
電源部が最初の計画と変わりました(最初はプリ部の電源とドライブ部の電源の2台)。
其れを片chのプリ部とドライブ部を一つのシャシにしました。
結果、本体側のメタコンの位置を変更しないといけなくなりました。
メタコンが並んだリアパネルだけ作り直しです。
トランスケースの穴開けは大丈夫だろうか?
今回、シャシの外に10個のトランスが付きます。
裸のトランスですからケースは必須(高圧が掛かっている端子がむき出し)。
なにしろ2年以上前に引いた図面です。細かな穴位置が・・・・・・・。
仮組みをして確認です。
エーーー、バッチリ。と言いながらOPTケースの側板を作っていないのに気付いたりして・・(大汗)。
外寸は出来ているので穴開けネジ切りだけです。
写真の説明。
細長い2個のケース。イコライザー段のトランスが片側3個入ります。
手前の中途半端な壁がOPTケースの一部。
穴が4個開いていますが、此れは出力端子の穴です。
トランスから出ますから、シャシに穴を開けると配線が長くなります。
ケースに付けてしまえば簡単です(実はこれも忘れていて・・・・汗)。
電源部が最初の計画と変わりました(最初はプリ部の電源とドライブ部の電源の2台)。
其れを片chのプリ部とドライブ部を一つのシャシにしました。
結果、本体側のメタコンの位置を変更しないといけなくなりました。
メタコンが並んだリアパネルだけ作り直しです。
トランスの予備配線が終わりました。
数えて見て自分でもビックリ。
左右で18個のトランスが乗ります。金額の事は考えません(大汗)。
もう、自分用のプリアンプは此れが最後だよね。
そんな訳で、『まあいいか。』は絶対にNG。
プリアンプ天板へ、小物パーツの取り付け開始。
前にアップしましたけど、兎に角穴が多い。
正直、穴開け加工中に、この穴は何の為にあけるんだっけ?
2年半前に書いた図面ですので、細かな事は見事に忘れています。
で・・・・・・。

小物パーツが全て付いた。
全ての穴が塞がった(残りはトランス関係の穴のみ)。
シッカリと図面を書いておいたので、何も考えずに図面の指定通りにパーツを付けたのです。
図面を省略していたら・・・・(冷汗)。
トランスを取り付ける前に、アースライン、ヒーター配線、B電源辺りの配線を始めます。
トランスをつけちゃうと重くて苦労が見えますので・・・。
数えて見て自分でもビックリ。
左右で18個のトランスが乗ります。金額の事は考えません(大汗)。
もう、自分用のプリアンプは此れが最後だよね。
そんな訳で、『まあいいか。』は絶対にNG。
プリアンプ天板へ、小物パーツの取り付け開始。
前にアップしましたけど、兎に角穴が多い。
正直、穴開け加工中に、この穴は何の為にあけるんだっけ?
2年半前に書いた図面ですので、細かな事は見事に忘れています。
で・・・・・・。
小物パーツが全て付いた。
全ての穴が塞がった(残りはトランス関係の穴のみ)。
シッカリと図面を書いておいたので、何も考えずに図面の指定通りにパーツを付けたのです。
図面を省略していたら・・・・(冷汗)。
トランスを取り付ける前に、アースライン、ヒーター配線、B電源辺りの配線を始めます。
トランスをつけちゃうと重くて苦労が見えますので・・・。
2台の電源が完成。
ついに本体に掛かります。
で、まず下準備。
今回のプリアンプ。兎に角沢山のトランスが入ります。
此処で問題なのが、僕愛用のトランス。
色々な使い方が出来るのですが、使用目的に合った結線をしないといけません。

その中の一つのトランス。左右で1個ずつ。
図面を見て下さい。こんなに予備配線が必要なんですね。
で、トランスのサイズ。

老眼の進んだ目にはきつい(汗)。
でも写真でお判りでしょうが、予備配線は終わっています。
なんか以前よりも上手くなった様な・・・・・・。
で、納得。
最近、Nゲージで無茶苦茶細かな作業を強いられています。
それと比べたら簡単なんですね(笑)。
今日はこれから雑用。
残りのトランスの予備配線は明日掛かります。
ちなみに、予備配線に使う材料は極細の錫メッキ線とテフロンチューブ(半田の熱で溶けない)。
どちらもネットで入手出来ます。
勿論フラックスは良質な物。半田のツキの良い酸性の物はNGです。
ついに本体に掛かります。
で、まず下準備。
今回のプリアンプ。兎に角沢山のトランスが入ります。
此処で問題なのが、僕愛用のトランス。
色々な使い方が出来るのですが、使用目的に合った結線をしないといけません。
その中の一つのトランス。左右で1個ずつ。
図面を見て下さい。こんなに予備配線が必要なんですね。
で、トランスのサイズ。
老眼の進んだ目にはきつい(汗)。
でも写真でお判りでしょうが、予備配線は終わっています。
なんか以前よりも上手くなった様な・・・・・・。
で、納得。
最近、Nゲージで無茶苦茶細かな作業を強いられています。
それと比べたら簡単なんですね(笑)。
今日はこれから雑用。
残りのトランスの予備配線は明日掛かります。
ちなみに、予備配線に使う材料は極細の錫メッキ線とテフロンチューブ(半田の熱で溶けない)。
どちらもネットで入手出来ます。
勿論フラックスは良質な物。半田のツキの良い酸性の物はNGです。
数日前から掛かっているプリの電源部。
本日午後、1台完成。
直ぐに2台目に掛かります。
1台目で組む手順が判ったので2台目は早いと思います。
で、トランスケースのアルマイトが仕上がったと連絡が来ました。
一色ですけど点数が多いので其れ成りの値段・・・・・・。
週明けに貰って来て、直ぐに彫刻屋さん。
チャクチャクと進んでいます。
本日午後、1台完成。
直ぐに2台目に掛かります。
1台目で組む手順が判ったので2台目は早いと思います。
で、トランスケースのアルマイトが仕上がったと連絡が来ました。
一色ですけど点数が多いので其れ成りの値段・・・・・・。
週明けに貰って来て、直ぐに彫刻屋さん。
チャクチャクと進んでいます。
昨日は片側のアースラインを引き終えました。
で、アースラインの引き回し方。

上が普通の回路図の書き方です。回路図的にはOKですが実際の引き回しではNGです。
実際の引き回しは下の方が正解です。
で・・・・・・(笑)。
ケミコンが3個封入されているブロックケミコンを使うと、自動的に下の配線に成ります。
ブロックケミコンって非常に便利なのですが音質的には・・・?
で、アースラインの引き回し方。
上が普通の回路図の書き方です。回路図的にはOKですが実際の引き回しではNGです。
実際の引き回しは下の方が正解です。
で・・・・・・(笑)。
ケミコンが3個封入されているブロックケミコンを使うと、自動的に下の配線に成ります。
ブロックケミコンって非常に便利なのですが音質的には・・・?
二日間、サボりました。雑用がたまりにたまって・・・。
そんな訳で配線は今日からスタートです。
暫くぶりのプリなので要領が悪い(下準備をしておけば簡単だったのにって・・・)。
配線の引き回しには迷いません。自分の法則が出来ているので、其れに忠実に引き回すだけです。
で、例のアースライン。

5Pの3番ピンを手前の4Pラグのセンターへ繋ぎます(つまり此処がアースポイント)。
あ、電流が流れる訳ではないので、手近の所へ落としただけです。
どこでもかまいません。
で、フローティング配線。

ドライブ段のヒーター巻き線(12,6V)。
此処から出ている配線は・・・・・。

5Pソケットの1番と2番へ接続。何処もシャシに落としていないんです。
落としちゃダメなんですよね(笑)。
アースを落とす基本。インピーダンスの高い方で落とす事。
ピンケーブルも同じです。
そんな訳で配線は今日からスタートです。
暫くぶりのプリなので要領が悪い(下準備をしておけば簡単だったのにって・・・)。
配線の引き回しには迷いません。自分の法則が出来ているので、其れに忠実に引き回すだけです。
で、例のアースライン。
5Pの3番ピンを手前の4Pラグのセンターへ繋ぎます(つまり此処がアースポイント)。
あ、電流が流れる訳ではないので、手近の所へ落としただけです。
どこでもかまいません。
で、フローティング配線。
ドライブ段のヒーター巻き線(12,6V)。
此処から出ている配線は・・・・・。
5Pソケットの1番と2番へ接続。何処もシャシに落としていないんです。
落としちゃダメなんですよね(笑)。
アースを落とす基本。インピーダンスの高い方で落とす事。
ピンケーブルも同じです。
昨日アップしました電源シャシ内部。
もう少し詳しく説明しますね。
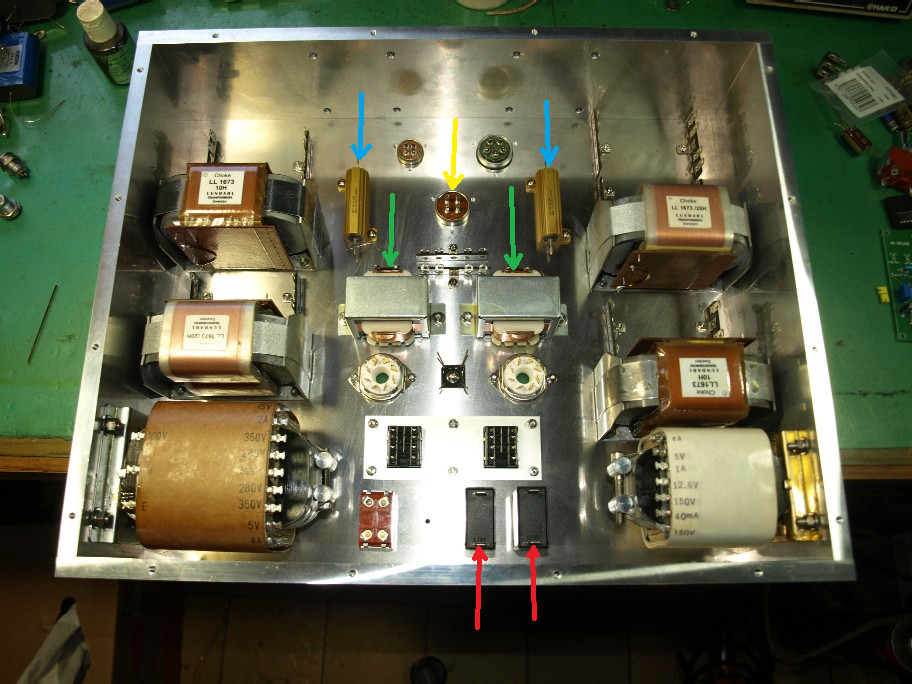
手前両端が電源トランス。その上二つが其々のチョークトランスです。
チョークインプットの場合、1個のチョークではリップルを取り切れません。
その様な訳で2個のチョークを使います。
回路としては、整流管→チョーク→コンデンサー→チョーク→コンデンサー、更に此の後に青矢印のメラルクラッド抵抗器→コンデンサーで終了です。
整流管ソケットに挟まれている四角のパーツ。
ヒーター整流用のブリッジダイオード。緑矢印の2個のチョークがヒーターのリップルフィルターです。
流石に此処はコンデンサーインプット(笑)。単なる抵抗負荷で電流値が一定ですので、此れでOKです。
コンデンサーインプットの場合、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧を調整出来ますので便利です。
黄矢印のメタコンはAC電源用。得意のスタッカードですので4Pが必要に成ります。
その後の二つのメタコン。4Pは其々のB電源出力。
5Pは其々のヒーター出力です。ドライブ段のヒーターはAC点火です。
で余った1P。此れがアンプ本体と繋がるアースラインです。
此れが有るので電源回路をフローティング出来るんですね。
赤矢印は其々の電源トランスに入るブレーカー。
基本的にヒューズは使いません。
ブレーカー後の2個の四角なソケット。タイマーとリレーのソケットです。
使う理由はこの後説明しますね。
あ、ブレーカーと電源SWの間の小さな穴。
LED用の穴です。何色にしようかなー・・・・。
先日出しました、トランスケースのアルマイト加工。
まだ、上がって来ていません。勿論値段も・・・・・。
今回は一色なので、前回の様な値段には成らないかと・・・・(チョイ怖い)。
その後彫刻も有りますし・・・。
もう少し詳しく説明しますね。
手前両端が電源トランス。その上二つが其々のチョークトランスです。
チョークインプットの場合、1個のチョークではリップルを取り切れません。
その様な訳で2個のチョークを使います。
回路としては、整流管→チョーク→コンデンサー→チョーク→コンデンサー、更に此の後に青矢印のメラルクラッド抵抗器→コンデンサーで終了です。
整流管ソケットに挟まれている四角のパーツ。
ヒーター整流用のブリッジダイオード。緑矢印の2個のチョークがヒーターのリップルフィルターです。
流石に此処はコンデンサーインプット(笑)。単なる抵抗負荷で電流値が一定ですので、此れでOKです。
コンデンサーインプットの場合、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧を調整出来ますので便利です。
黄矢印のメタコンはAC電源用。得意のスタッカードですので4Pが必要に成ります。
その後の二つのメタコン。4Pは其々のB電源出力。
5Pは其々のヒーター出力です。ドライブ段のヒーターはAC点火です。
で余った1P。此れがアンプ本体と繋がるアースラインです。
此れが有るので電源回路をフローティング出来るんですね。
赤矢印は其々の電源トランスに入るブレーカー。
基本的にヒューズは使いません。
ブレーカー後の2個の四角なソケット。タイマーとリレーのソケットです。
使う理由はこの後説明しますね。
あ、ブレーカーと電源SWの間の小さな穴。
LED用の穴です。何色にしようかなー・・・・。
先日出しました、トランスケースのアルマイト加工。
まだ、上がって来ていません。勿論値段も・・・・・。
今回は一色なので、前回の様な値段には成らないかと・・・・(チョイ怖い)。
その後彫刻も有りますし・・・。
